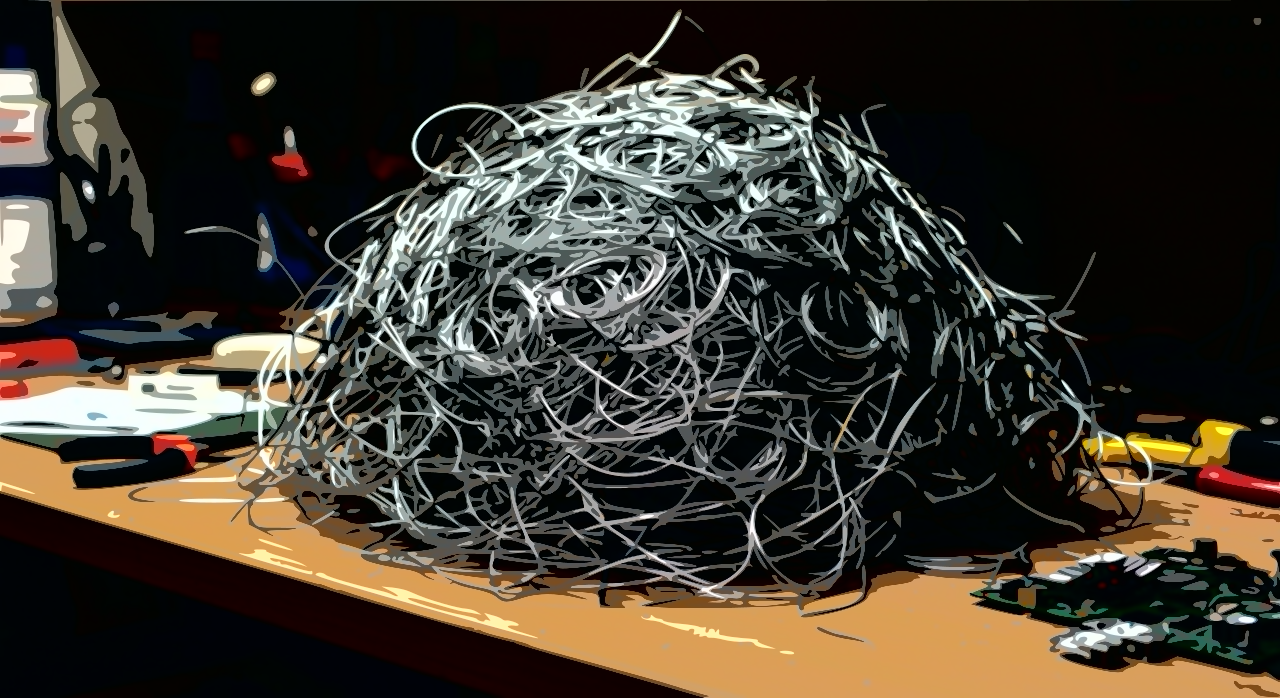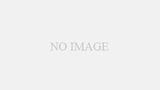ニッパー&ラジオペンチって何に使う?
電気工作や電子部品のDIYでは、はんだごてと並んで使う頻度が高いのが「ニッパー」と「ラジオペンチ」です。
形状が一見似ている2つの道具ですが、役割や選び方に違いがあります。
はんだ付けする前や後のリード線(部品の足)のカットや、細かい部品の保持・曲げ加工・取り回しに活躍してくれる、まさに手先の延長とも言える存在。初心者のうちに、良いものを1本ずつ持っておくと、DIYのストレスがぐっと減ります。
ニッパーとは?どんな作業で使う?
ニッパーは、部品のリード線(足)や細い配線を切るための工具です。
基板から飛び出た部品の足を切ってきれいに仕上げたりできるため、はんだ付け前後の処理や基板作業には欠かせません。
電気工作向けのニッパー選びのポイント
- 先端が細くて刃が薄く鋭いもの(狭い場所でも切れる)
- 切断面をきれいに仕上けたいならフラッシュカットタイプの精密ニッパー
- 刃の硬さやバネの有無(連続作業が楽になる)
- 安物はすぐ刃が欠けるので注意
💡 ニッパーは精密な作業向けなので、硬いステンレス線や太い金属線を無理に切ろうとすると刃が欠けたりして傷んでしまうことがあります。
このような硬い素材を切断したい場合は、「倍力タイプの金切り鋏」や「専用のワイヤーカッター」などを併用するのが安全で長持ちのコツです。
また、100円ショップなどで売っている安価なニッパーも、使いどころを考えれば意外と便利。
たとえば「どうしても少し硬めの線を切りたいけど、良いニッパーの刃を傷めたくない」場面などでは、使い捨て感覚で安いニッパーを使うと安心して作業ができます。
ラジオペンチとは?どう使う?
ラジオペンチは、細かい部品をつまんだり、リード線や細い金属線を曲げたりするのに使う定番工具です。
先が細くなっているため、狭い場所の作業や、部品の整形にも非常に役立ちます。
電気工作でのラジオペンチの活用例
- 抵抗のリード線を直角に曲げて基板に差し込む
- コネクタのピンの整形や仮止め
- 細い線をつかんで引き出す
- リード線を部品に巻き付けてしっかりはんだ付けしたい時の下処理
💡 大小2種類のラジオペンチを揃えておくと、作業の幅がグッと広がります。
小型は狭い部分や繊細な作業に、大型は力が必要な作業に向いています。
💡 また、2本のラジオペンチを使って、片方で固定しながらもう一方で線を曲げたり、ねじったり、まっすぐに伸ばしたりといった作業ができるため、非常に効率的かつ正確な加工が可能になります。
電気工作向けラジオペンチの選び方
- 先端が細く、しっかり閉じるタイプ
- ギザギザが浅め(部品を傷つけない)
- バネ付きで作業が楽
- ワイヤーストリッパー付きの複合型も便利なことも
✨ ラジオペンチは使い心地の差が出やすい工具。ちょっといい物を選ぶと、指先の延長としての精度がぐっと上がります!
ニッパーとラジオペンチの使い分けまとめ
| 用途 | ニッパー | ラジオペンチ |
|---|---|---|
| 配線を切る | ◎ | △(無理に切ると刃が欠けます) |
| 部品の足を整える | ◎ | ◎ |
| 部品をつかむ | × | ◎ |
| 配線を曲げる | △ | ◎ |
| はんだ前の調整 | ◎ | ◎ |
あると便利!+αの工具
- 強力ニッパー → 刃が頑丈で、硬い鋼線も切断できる
- ベントタイプのラジオペンチ → 奥まった部品のつかみに便利
- 圧着付きタイプ → 圧着端子のカシメもできる
安物を選ぶと後悔する?
ニッパーもラジオペンチも、100円ショップや格安工具セットに入っているものでも一応使えます。
しかし、切れ味が悪い・刃こぼれしやすい・握りにくい・精度が悪いなど、長く使うにはストレスになることも。
特にニッパーは、刃の合わせ精度が悪いと細かい作業に支障が出ます。
「最初から高級品じゃなくていいけど、最低限ちゃんと使える物を」選ぶのがコツです。
どれを買うか迷ったら……おすすめのラジオペンチメーカー
ラジオペンチは、見た目が似ていても精度や耐久性、作業性に大きな違いがあります。
特に電気工作では、先端の合いの良さや握りやすさが重要です。
以下に、初心者から上級者までおすすめできる信頼性の高いメーカーを紹介します。
1. ENGINEER(エンジニア)
精密作業向け工具で定評のある日本メーカー。先端精度が高く、グリップもしっかりしていて長時間使っても疲れにくい。細かい電子部品作業にぴったり。
2. HOZAN(ホーザン)
電気・電子系工具の老舗。品質が高く、価格も比較的手ごろ。学校や工業高校、プロ現場でも使用されている定番ブランドです。
3. KNIPEX(クニペックス)
ドイツの一流工具メーカーで、握りやすさ・強度・耐久性は抜群。価格はやや高めだが、工具にこだわる人にはぜひ使ってみてほしい逸品。
4. VESSEL(ベッセル)
ドライバーで有名なメーカーだが、ペンチやラジオペンチ類も使いやすくて信頼性が高い。日本製らしい丁寧な作りでコスパ良し。
5. TONE(トネ)
本来は自動車整備などの工具に強いが、ペンチ類も高品質。やや太めのグリップで力が入れやすく、太めの線材加工にも対応しやすい。
番外編:100均のラジオペンチ
一部の100均工具も意外と使えることがありますが、精密な作業や連続使用には向いていません。
サブツールや屋外用、気軽な作業用に使い分けるのがおすすめです。
必要に応じて「先が細め」「バネ付き」「絶縁グリップあり」などの仕様もチェックすると、自分の用途に合った1本が見つかりやすくなります!
ニッパーとラジオペンチの手入れ、してますか?
電気工作でよく使うニッパーやラジオペンチですが、ちゃんと手入れしていますか?
どんなに良い工具でも、放っておけばサビたり動きが悪くなったりしてしまいます。
特に日本のような湿気の多い環境では、油断するとすぐに錆びてしまうので、以下のポイントに注意しましょう。
工具を濡らさない!
- 使用後に汗や水分がついたままだと、すぐにサビの原因になります。
- 特に稼働部(結合部・ジョイント部)がサビると動きが渋くなり、使いづらくなるだけでなく、無理な力がかかって破損の原因にも。
使用後は軽く拭いておく
- 使った後は、乾いた布やティッシュで金属部分の汚れや指紋を拭き取るだけでもOK。
- 金属粉や油分がついている場合は、中性洗剤を少しつけた布で拭いた後、乾いた布でしっかり水分を取ってあげましょう。
稼働部には定期的に油をさす
- 稼働部分(軸のところ)には防錆用のオイルや潤滑スプレー(CRC-556など)をほんの少し差しておくと、動きがスムーズでサビ予防にもなります。
- オイルをさしたら、数回動かしてなじませ、余分な油は拭き取っておきましょう。
保管は風通しのよい場所で
- 工具箱や引き出しの中でも、シリカゲル(乾燥剤)を入れておくと湿気対策になります。
- サビ防止のために、工具を新聞紙で包んでおくというアナログな方法も有効です。
まとめ:日々のひと手間で長く使える!
ニッパーやラジオペンチは、ちょっとした手入れと扱いの工夫で、何年も快適に使い続けられる大事な相棒になります。
実際、私なんかは中学生の頃に購入したニッパーとラジオペンチを、手入れしながら30年近く今も愛用しています。
少しずつくたびれてきてはいますが、今でも現役で大活躍中です。
手入れの習慣をつけておけば、作業中に「動きが悪い」「切れ味が悪い」なんてストレスも減って、より快適にDIYを楽しめますよ!
最後に はじめの一本は“手に馴染む”ことが大事!
ニッパーやラジオペンチは、実際に使ってみないと使いやすさがわからない道具でもあります。
レビューや評判を参考にしつつ、自分の手に合った道具を選ぶことが、DIY作業を楽しくスムーズにする第一歩です!