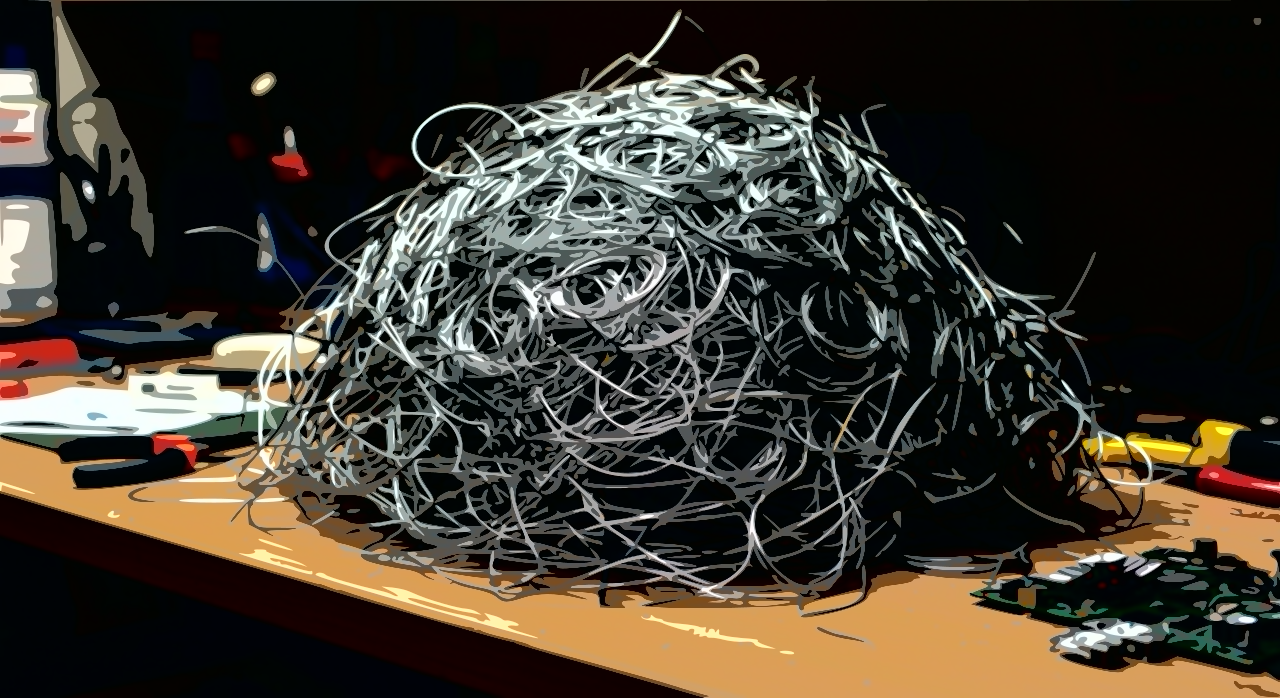- 電気工作に必須のはんだごて
- はんだごてって何する道具?どうして必要なの?
- はんだごての主な種類と特徴
- 実はとても重要、はんだごてのコテ先の形状
- はんだごてのW数で分かれる用途
- 安すいはんだごてに有り勝ちな落とし穴
- 最初の1本は“失敗しない”ことが一番大事!
- 信頼できるおすすめはんだごてメーカー紹介
- はんだごてと一緒に「はんだ」の種類も知っておこう!
- はんだこての紹介の最後に
電気工作に必須のはんだごて
電気工作を始めようと思ったとき、真っ先に必要になるのが「半田ごて」です。
でも、いざ買おうとすると……
- 「種類が多すぎて何がいいかわからない」
- 「安い半田ごてで大丈夫?」
- 「温度調節って必要なの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では半田ごての種類と特徴、おすすめの選び方をわかりやすく解説します!
はんだごてって何する道具?どうして必要なの?
半田ごては、電子部品や配線を「はんだ」と呼ばれる金属でつなぐための熱工具です。
例えば……
- LEDを点灯させる
- マイコンボードにセンサーを接続する
- 電子キットを組み立てる
といったDIYにおいて、なくてはならない存在。電気工作の心臓部とも言える道具なんです。
はんだごての主な種類と特徴
一口に「はんだごて」と言っても、その種類は実にさまざまです。
たとえば加熱方式の違いで分類するだけでも、「電気式」と「ガス式(ややマイナー)」があります。
電気式はさらに細かく分けられます。
- AC100Vのコンセント式
- USB給電などのDC電源式
- リチウムイオン電池を内蔵したコードレスタイプ(充電式)
さらに、同じ電気式でも:
- セラミックヒーター式/ニクロムヒーター式といった発熱素子の違い
- こての形状(ストレート型・ガンタイプなど)
- 温度調整の有無(ダイヤル内蔵型/ステーション型)
- 加熱速度(瞬間加熱の可否)
- こての出力(W数)
……など、比較ポイントがたくさんあります。
また、価格帯も数百円のエントリーモデルから、数万円のプロ仕様まで非常に幅広く、用途やスキルに応じた選び方が大切です。
そこで、以下に代表的なはんだごての種類と、それぞれの特徴を一覧表にまとめました。購入時の参考にぜひどうぞ。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いている人・用途 |
|---|---|---|---|---|
| スティック型(ニクロムヒーター式) | コンセント直結/昔ながらの加熱構造 | 安価・構造が単純 | 温度不安定・寿命短め | 入門向け/簡易作業に |
| 温調付きはんだごて(セラミック式) | ダイヤル調整付き/温度安定 | 幅広い作業に対応 | 少し高価 | 初心者〜中級者向け |
| セラミックヒーター式(スタンダード) | 急速加熱・耐久性高 | 安定した性能 | 安価品はムラあり | 中級者〜 |
| バッテリー式コードレス | 充電式/USBや専用充電で使える | 配線不要・取り回し◎ | パワー&持続時間に限界 | 出先での軽作業に |
| ガス式はんだごて | 火気で加熱/電源不要 | 屋外・災害時にも便利 | 火災リスク・調整に慣れ必要 | 屋外整備・応急用途 |
| ステーション型(セラミック式) | 温調ユニット分離/こて先交換可 | 長時間作業◎・高性能 | 高価・据え置き型 | 頻繁に使う人・プロ |
| ネジ式こて先交換型 | 工具なしでこて先交換可 | 用途ごとに柔軟対応 | 専用先端が必要な場合も | 初〜上級者まで |
| ガンタイプ(トランス加熱式) | 引き金式/瞬間高熱 | 立ち上がりが速い | 大きく重め/精密作業不可 | 配線や大型部品処理に |
各はんだこての補足説明
スティック型(電気式・非温調)
もっともベーシックな形状のはんだごてで、AC100Vの電源にそのまま繋いで使います。
温度調整機能はなく、スイッチもないものが多いため、初心者が扱うには少し注意が必要。
とはいえ価格が非常に安く、ちょっと試してみたい方や、教材として使うにはぴったりです。
温調付きはんだごて(ダイヤル式)
こて本体に温度調整用のダイヤルが付いており、作業内容に応じて加熱温度を変更できます。
セラミックヒーター式が主流で、立ち上がりも早く、熱の保持も安定。DIY用途から趣味レベルの電気工作には非常におすすめです。
ステーション型(温調ユニット別体)
こてと温度調整ユニットが別になった本格派モデル。
細かな温度制御が可能で、基板のリワークや精密部品の取り扱いにも対応します。
高価ですが性能は段違いで、電気工作が本格的な趣味になってきた方には最適。
バッテリー内蔵・コードレスタイプ
リチウムイオン電池などを内蔵したコードレスタイプ。
USB充電で持ち運びにも便利ですが、加熱時間が短かったりパワー不足な製品もあるため、使用時間や作業内容に応じた選び方が必要です。
野外作業や一時的な使用には非常に便利。
ガス式はんだごて
専用ガスやカセットガス、ライター用のガスを燃料とし、電源が取れない場所でも使える利点があります。
火を使うため屋内ではやや扱いに注意が必要ですが、アウトドアや緊急時の作業には心強い味方です。
はんだ付けだけでなく、熱収縮チューブの加熱などにも使えるモデルも。
ガンタイプ(ピストル型)
トリガーを引くことで加熱が始まる構造。
通常のスティック型より加熱が早く、大きなコネクタや太いケーブルなど、熱容量が必要な場面に適しています。
一方で細かい作業にはやや不向き。
こて先交換式(ネジ式)
ネジでこて先を簡単に交換できるタイプ。
細いチップから幅広タイプまで、用途に応じたこて先を使い分けられるため、1本持っておけばさまざまな作業に対応できます。
交換時に専用工具が必要な場合もあるため確認を。
ニクロムヒーター式
セラミックヒーター式に比べて加熱が遅く、温度の安定性にも欠けますが、非常に安価でシンプルな構造のため、教育用途や一時的な使用には重宝されます。
現在ではセラミックヒーター式が主流ですが、ニクロム式にも根強いファンがいます。
実はとても重要、はんだごてのコテ先の形状
はんだ付けの出来栄えや難易度を大きく左右するのが、半田ごての「コテ先の形状」です。
意外と見落とされがちですが、腕以上に実はこの形状選びこそが“うまくはんだ付けできるかどうか”のカギになります。
用途に合っていないコテ先を使ってしまうと、熱がうまく伝わらなかったり、はんだが広がりすぎたりと、作業が難しくなってしまう原因に。
とくに安価なエントリーモデルによくある「ペンシル型(円錐型のB型やI型)」は一見扱いやすそうですが、熱伝達効率が低く電子部品の基板作業にはあまり向いていない場合があります。
以下に、代表的なコテ先の形状と、その特徴・用途をまとめました。
主なコテ先の形状と特徴
| 形状 | 特徴 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| I型(尖った円錐形) | B型の先端をさらに細くした形状、ピンポイント加熱が可能 | 極小部品取り付けや微細な補修作業用だが、実は使いにくい | 熱容量が小さく、広い範囲には不向き、これを選択する機会はほとんどない |
| C型(斜めカット) | 先端が斜めにカットされており、角でも面でも使える | 基板のはんだ付け全般、リード線など | 万能タイプとして人気。迷ったらコレ |
| D型(平型・マイナスドライバー状) | 接触面が広く熱伝導が良い | 電源ラインや大きなランド面など、熱をしっかり伝えたい場面 | 先端の幅が広いものは小さい部品の作業には不向き |
| K型(ナイフ型) | 鋭角な先端を立てて狭小スペースに点で、刃面を寝かせて幅広く加熱等、多用途、しかしホットナイフ代わりにはなりません | リワークやチップ部品の取り外し、流しハンダなど | 慣れが必要だが万能性が高い |
| B型(ペンシル型・丸型) | 先が丸く、部品への熱伝達効率は悪い | 安いはんだこてに付属するのはほとんどB型、向いた作業はない | 部品に熱を伝えにくく、作業全般的に不向き |
コテ先の交換で作業効率が激変!
はんだごての中には、コテ先を簡単に交換できるモデルもあります。作業ごとにコテ先を変えることで、はんだの乗りやすさ・きれいさ・作業効率が格段にアップします。
たとえば……
- 「細かい配線を修正したい」→ I型またはK型
- 「電源ラインをしっかり固定したい」→ D型で面加熱
- 「とにかくオールラウンドに使いたい」→ K型
作業対象に合わせてコテ先を選ぶことは、プロも実践している基本テクニックです。初心者の方も、いや初心者だからこそ、ぜひ「コテ先選び」に注目してみてください!
はんだごてのW数で分かれる用途
はんだごてを選ぶ際に見逃せないのが「W(ワット)数」。
これはつまり、どれだけの熱量(パワー)を発揮できるかを表しています。
同じ形のはんだごてでも、W数が違えば加熱速度や熱保持力が大きく変わってきます。
用途に合ったW数を選ぶことで、よりスムーズにはんだ付けができるようになります。
目的別・W数の選び方の目安
| W数の目安 | 特徴 | 向いている作業 |
|---|---|---|
| 20〜30W | 熱量が小さく、加熱に時間がかかるが安全 | 小型の電子工作、熱に弱い電子部品、ICソケット、細かい配線の修正など |
| 30〜50W | 一般的なDIY用で最も汎用性が高い | 電子工作全般、基板上の部品交換、LED工作など |
| 60W以上 | 加熱が速く、熱保持力も高い | 電源ラインのはんだ付け、大きな端子、太い線材、金属同士の接合など |
W数が高ければいいとは限らない!
W数が高ければ短時間で高温になり、加熱力は強くなりますが、小さい部品には熱をかけすぎて破損の原因になることもあります。
逆に、W数が低すぎると、熱が十分に伝わらずはんだがうまく流れないといった問題も。
ポイント:W数は「作業対象のサイズ」で選ぶ!
- 小型基板や細かい部品中心 → 20〜30W
- 電子工作全般を幅広くカバー → 30〜50W
- 電源回路や太いケーブルなど熱容量の大きな対象 → 60W以上
最近では、温度調整機能付きのはんだごてであれば、W数が高くても温度を下げて使えるものが多く、より柔軟な作業が可能です。
自分の用途や作業内容に合わせて、最適なW数を選びましょう!
安すいはんだごてに有り勝ちな落とし穴
私は安いはんだごてを否定するつもりはまったくありません。
実際、私自身も500~1,000円くらいの安価なはんだごてを何本も持っていますし、用途に応じて使っています。
しかし、安価なはんだごてには“地雷”も潜んでいるため、特に初心者の方には注意してほしいポイントがいくつかあります。
安物はんだごてでよくあるトラブル
- 温度が安定しない
→ 加熱しすぎたり、逆に熱が足りなかったりして、部品を傷める原因になります。 - こて先がすぐ酸化する・交換できない
→ はんだの乗りが悪くなり、作業が進まない・仕上がりが悪いなどのトラブルが発生。こて先交換不可なタイプは、使い捨て感覚になってしまいます。 - 絶縁や安全性に不安がある
→ 安全基準が不明な製品もあり、漏電や火傷のリスクもゼロではありません。
結果として……
- 最初は使えても、徐々にストレスが増える
- 経験が増えてくると、温調機能や交換式コテ先の必要性を痛感し、いずれ買い替えることに
- 最終的に「安物買いの銭失い」になりやすい
それでも“完全に無駄”ではない!
とはいえ、安いはんだごてははんだ付け以外にも使い道があります。
- プラスチックの加工や熱収縮チューブの加熱など、「本来の用途外」で活躍する場面も。
- 使えなくなった場合でも、コンセントコードやヒーター部分など、パーツとして再利用することも可能。
- ある程度経験を積んだ方なら、「敢えて安いはんだごてを使う」シーンも出てきます。(例:使い捨て前提の作業、荒仕事など)
まとめ
初心者の方には「値段の安さだけ」で選ぶのはおすすめできません。
安価なはんだごてを買うなら、そのメリットとデメリットを理解した上で、目的に応じて使い分けるのがベストです。
最初の1本は“失敗しない”ことが一番大事!
初心者だからこそ、最初に選ぶはんだごては“信頼できるもの”を選ぶことが大切です。
多少価格が高く感じるかもしれませんが、
・長く安心して使える
・作業の上達にもつながる
・はんだ付けが楽しくなる!
というメリットを考えれば、良い選択は「投資」になります。
うまくはんだ付けできると、工作は一気に楽しくなる!
はんだがうまく乗り、狙った通りに部品がきれいに接合できると、電子工作が一気に楽しく感じられます。
「自分にもできた!」という体験は、モチベーションに直結します。
逆に、安定しない道具でうまくいかないと、すぐに「自分には無理かも…」と挫折してしまう原因に。
だからこそ、最初の1本選びはとても重要なんです。
経験からおすすめする「最初の1本」
私の経験から見て、初心者に最もおすすめしたいのは次のようなはんだごてセットです。
温度調整機能付き・こて先が複数付属・交換可能なタイプ
このタイプが初心者におすすめな理由
- 温度調整ができる → 部品に応じて温度を最適化でき、ミスが減る
- こて先を交換できる → 用途に応じた先端形状で作業がしやすい
- 将来的にも使い続けられる → 慣れてきても買い替えの必要がない
結果として、最初に少し良いものを選ぶことで、後悔しにくく、無駄な買い直しも避けられるます。
信頼できるおすすめはんだごてメーカー紹介
はんだごて選びで迷ったら、「信頼できる国内メーカー」から選ぶのが安心です。
以下は、日本国内での半田ごて販売に実績があり、多くの愛用者に支持されているおすすめメーカーです。
ホーザン(HOZAN)
- 特徴:工具メーカーとしての総合力が高く、電子工作全般に対応した製品を多数展開。
- 初心者セットも充実しており、温度調整付きのはんだごてや工具一式が揃ったスターターキットも人気。
- 安心の品質管理とアフターサービスも強み。
初心者にも扱いやすい設計と耐久性を両立。セットで揃えたい方に特におすすめ!
白光(HAKKO)
- 特徴:業務用・プロユースでも高評価のメーカー。精密作業に強い。
- こて先交換式・温調機能付きの定番モデル「FX-600」など、DIY愛好家にも人気。
- 消耗品(こて先やヒーター部品)も手に入りやすく、長く使い続けやすいのが魅力。
一生モノのはんだごてを探している方に。安心と実績のあるメーカーです。
日本ボンコート(BONKOTE)
- 特徴:特殊はんだごてや微細作業向け製品に強み。ニッチながら熱狂的な支持がある。
- 特に精密用途やマニアックな改造用途での活用例が多い。
- 製品の個性が強く、「わかる人にはわかる」メーカー。
上級者向けに。人と違ったこてを探している人にハマる可能性あり!
太洋電機産業(goot)
- 特徴:コスパと機能性のバランスが良く、一般ユーザーから業務用まで幅広く支持されている。
- 人気の温調式「PXシリーズ」など、価格帯のバリエーションも豊富。
- 消耗品やこて先の入手もしやすく、定番を選びたい方にぴったり。
「はじめての1本」から「長く使えるモデル」まで、迷ったら goot!
石崎電機製作所(SURE)
- 特徴:電熱機器全般に強い老舗メーカー。工業用やホビー用の加熱工具も豊富。
- はんだごてだけでなく、熱加工系のDIYツール全般に信頼性がある。
- 比較的価格は抑えめで、実用性重視のユーザーにおすすめ。
“ザ・道具”という堅牢な使い心地。実用派DIYer向け。
まとめ:メーカー選びに迷ったら…
| メーカー名 | 特徴キーワード | 向いている人 |
|---|---|---|
| ホーザン(HOZAN) | 初心者セット・耐久性・汎用性 | 初心者〜中級者、工具も揃えたい人 |
| 白光(HAKKO) | 精密作業・プロ仕様・安心感 | 長く使いたい人、上達したい人 |
| 日本ボンコート | 個性派・特殊用途・マニア向け | マニア志向、変わり種を求める人 |
| 太洋電機産業(goot) | コスパ・定番・使いやすさ | 初心者〜中級者、無難に選びたい人 |
| 石崎電機製作所(SURE) | 電熱工具全般・実用性・価格控えめ | 実用重視派、他のDIY用途にも使いたい人 |
Amazonおすすめ半田ごてセット
Amazonでおすすめとなっている、これから電気工作を始めたい方にぴったりの「はんだごてセット」です。
セット内容は以下のとおり。
- 温度調整式のはんだごて本体
- 交換用コテ先
- ハンダ吸い取り器・吸い取り線
- スポンジ付きコテ台
- ピンセット など、合計14点セット!
ノーブランド品ですが、これだけ揃っていて、なんと2000円を切る価格。
もし何かの初期不良があってもAmazon出荷なので返品返金も保証されていて安心。
ハンダ付けに慣れるためのはじめての1本としては、性能・価格ともに非常にバランスが良く、個人的にも入門用にかなりおすすめのセットだと思います。
はんだごてと一緒に「はんだ」の種類も知っておこう!
はんだごてとセットで必ず必要になるのが「はんだ線」。
実はこの“はんだ”にもいくつか種類があり、用途や扱いやすさに差があります。
電子工作初心者が間違ったはんだを選んでしまうと、うまく溶けなかったり、部品を傷めたりする原因にもなるため、はんだの種類と特性もあわせて知っておくことが大切です。
はんだの分類①:有鉛はんだ vs 無鉛はんだ
| 種類 | 特徴 | 融点の目安 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 有鉛はんだ(Sn-Pb) | 錫(すず)と鉛の合金(例:Sn60/Pb40など) | 約183〜190℃ | 低温でよく溶ける/濡れ性◎/初心者に扱いやすい | 鉛を含むため健康や環境面の注意が必要 |
| 無鉛はんだ(Sn-Ag-Cu) | 錫に銀・銅などを加えた鉛フリー合金(例:Sn99.3/Ag0.3/Cu0.7) | 約217〜225℃ | 鉛フリーで環境・健康に優しい | 融点が高く、こての温度管理が難しい傾向 |
初心者やホビー用途では、有鉛はんだ(例:Sn60/Pb40、Sn63/Pb37)の方が扱いやすく、きれいに仕上がりやすいです。
ただし、作業後は手洗いをしっかり行うなど、安全への配慮は忘れずに!
はんだの分類②:フラックスあり vs フラックスなし
市販されているはんだ線には、「フラックス(ヤニ)」という薬剤があらかじめ芯に入っているタイプと、入っていないタイプがあります。
- フラックス入りはんだ:最も一般的。はんだ付け時にフラックスが流れて酸化を防ぎ、きれいな接合を助けてくれる。
→ 初心者は「ヤニ入りはんだ」と書かれた製品を選べばOK! - フラックスなしはんだ:別途フラックスを筆などで塗布する必要あり。工業用途や特殊用途で使用。
主なはんだ合金と特徴(まとめ)
| 主成分構成(例) | 名称・略称 | 融点 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|
| Sn60/Pb40 | 有鉛はんだ | 約183〜190℃ | 濡れ性が良く、初心者にも扱いやすい |
| Sn63/Pb37(共晶) | 有鉛共晶はんだ | 約183℃ | 電子工作の定番。融点が一定で作業しやすい |
| Sn99.3/Cu0.7 | 無鉛はんだ(鉛フリー) | 約227℃ | 比較的安価な無鉛はんだ。環境対応 |
| Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 | SAC305(無鉛) | 約217℃ | 高性能・高信頼性向け(工業用にも) |
| Sn-Zn | 錫・亜鉛はんだ | 約199℃ | 無鉛だが酸化しやすい。特殊な用途向け |
どのはんだを選べばいい?
電子工作初心者には、以下のようなはんだ線が扱いやすいです:
- 有鉛タイプ(Sn60/Pb40やSn63/Pb37)
- ヤニ入り(フラックス入り)
- 線径は0.6〜0.8mm程度(汎用性が高く、初心者向け)
補足:はんだにも適した温度がある!
無鉛はんだを使う場合、はんだごての出力や温度調整ができるタイプが望ましいです。
温度が低すぎると溶けにくく、高すぎると部品や基板を傷める原因になります。
「無鉛はんだを使いたいけど、はんだごては安物で温調がない…」という方は、有鉛はんだを検討するのも一つの手です。
初心者が避けるべきはんだ
はんだ選びでは、もちろん「適切な製品を選ぶこと」が重要ですが、逆に初心者が避けるべきはんだを知っておくことも大切です。
いくつかのタイプは、取り扱いが難しく、トラブルを引き起こす可能性が高いので、注意しましょう。
1. 安価すぎる無名ブランドのはんだ
- 特徴:価格が安いだけで品質が低い、フラックスの質が悪い、酸化が早い、融点が安定しない。
- 問題点:溶けにくい、煙が多く発生する、作業中にノズルが詰まりやすい、長期使用で部品を傷めるリスクが高い。
安すぎる無名ブランドのはんだを使うのは、初心者には特にリスクが大きいです。融点が不安定で作業が進まなかったり、部品にダメージを与えてしまうことがあります。
2. 鉛含有量が極端に多いはんだ
- 特徴:鉛含有率が高い(例:Sn40/Pb60など)、低価格で手に入ることが多い。
- 問題点:溶けやすいという利点はありますが、鉛を含んでいるため健康や環境に有害。手に付着した鉛を触ると危険な場合があるため、取り扱いに注意が必要。
鉛含有量が多いはんだは、使用する際に健康リスクを引き起こす可能性があるため、できるだけ避けましょう。
3. フラックスが含まれていないはんだ線
- 特徴:フラックスが入っていないため、はんだ付け時に別途フラックスを塗布しないといけない。
- 問題点:フラックスがないと、酸化を防げず、良好な接合ができません。高温で作業し続けると、はんだの浸透性が悪くなり、しっかりと接続ができないことが多いです。
フラックス入りのはんだ線を選ぶと、作業がスムーズに進み、後からフラックスを塗る手間が省けます。
4. 亜鉛や鉛以外の合金成分比が不明なはんだ
- 特徴:錫(スズ)以外の成分が不明なはんだ線や、亜鉛や鉛の含有量が極端に低いはんだ。
- 問題点:金属の成分が不明だと、溶ける温度や特性が読みにくく、作業の際に不安定になりやすい。品質にバラツキがあり、作業中のトラブルが増える可能性があります。
信頼できる製品を選ぶためにも、はんだ線に記載された成分や融点を確認しましょう。信頼のあるメーカーから選ぶのがベターです。
5. 低品質の低温はんだ(低融点)
- 特徴:低融点のはんだ(例えば、ガラスやプラスチックが溶ける温度以下で使用できるタイプ)など。
- 問題点:はんだがあまりに低温で溶けるため、作業中に接続部分がしっかりと固まらないことがある。接合強度が低く、電気的な接続に不安が残ります。
低温はんだは精密機器などでは便利ですが、安定した接続を求める場合には一般的な融点(183〜225℃)のものを選ぶ方が無難です。
まとめ:避けるべきはんだとは?
初心者が避けるべきはんだは、品質が低いものや、成分や特性が不明なもの、鉛を含み過ぎるものなどです。
選ぶ際には、信頼できるメーカーの製品を選び、あらかじめフラックスが入った線を使うことをおすすめします。
初心者の方は、最初は信頼のある有名メーカーのヤニ入り有鉛はんだを使って、作業に慣れてから、無鉛はんだや特殊用途のはんだにチャレンジすると良いでしょう。
はんだ選びで迷ったらこのメーカー
はんだを選ぶとき、品質や信頼性が最も重要です。そこで、初心者でも安心して使える、信頼の置けるメーカーを紹介します。
以下のメーカーは、長年の実績があり、電子工作の初心者から上級者まで、多くのユーザーに支持されています。
1. ホーザン(HOZAN)
- 特徴:日本の代表的な工具メーカー。高品質なはんだや精密作業用の工具を数多く取り扱っています。特に、はんだ線やはんだごては、信頼性が高く、初心者でも安心して使用できます。
- おすすめポイント:
- ヤニ入りの有鉛・無鉛はんだが豊富。
- はんだ線の太さや種類が豊富で、用途に合わせた選択が可能。
- 初心者向けのセット商品も取り扱っており、作業がスムーズ。
2. 白光(HAKKO)
- 特徴:世界的に有名なはんだごて・工具メーカー。精密はんだ付けに必要な製品を取り揃え、品質が非常に高いです。
「HAKKO」のはんだごてや関連製品は、業界標準としても広く使われており、信頼性抜群。 - おすすめポイント:
- はんだ線の品質が非常に良く、溶けやすく、しっかりと接合できます。
- 高性能な温度調整機能付きはんだごての人気も高い。
- 無鉛はんだの選択肢も多く、環境にも配慮された製品が多い。
3. 日本ボンコート(BONGARD)
- 特徴:特に電子機器や精密機器向けのはんだを得意とするメーカーです。日本国内で非常に人気があり、数多くの技術者が使用しています。
- おすすめポイント:
- 無鉛はんだや低温はんだなど、特殊な用途に対応した製品が揃っています。
- ヤニ入りはんだ線が初心者にも扱いやすい。
- 高い信頼性と耐久性を誇り、工業用途でも広く使用されている。
4. 太洋電機産業(TAIYO ELECTRIC)
- 特徴:はんだ関連の製品を豊富に取り揃える老舗メーカー。エレクトロニクス業界においては、非常に信頼性の高いメーカーとして知られています。
- おすすめポイント:
- 精密はんだ付けや配線作業に適した高品質な製品を提供。
- 無鉛はんだやフラックスが優れた性能を発揮する。
- はんだ線の種類が豊富で、用途に応じた選択肢が豊富。
5. 石崎電機製作所(ISHIZAKI)
- 特徴:高精度な電子機器を支える、はんだごてや工具を取り扱う日本のメーカー。特に、はんだごての温度調整機能やコテ先交換の精度が高い製品を提供しています。
- おすすめポイント:
- 初心者向けのはんだセットも充実しており、温度調整やコテ先交換ができるので、長く使える製品が多い。
- 使いやすさと精度に定評があり、無鉛はんだの取り扱いにも力を入れています。
- 高品質のはんだ線と、作業効率を高める工具類が豊富。
まとめ:信頼のあるメーカーで選ぼう!
初心者の方は、まずは信頼できる有名メーカーから製品を選ぶのが安心です。
上記の5つのメーカー(ホーザン、白光、日本ボンコート、太洋電機産業、石崎電機製作所)は、すべて高品質で使いやすく、初めてのはんだ付けでも扱いやすい製品が揃っています。
これらのメーカーを選ぶことで、より快適で安全な電子工作が楽しめることでしょう!
一歩踏み出して信頼のあるメーカーを選ぶことが、後々の作業の効率アップに繋がりますよ!
電気工作を本格的にやるなら、ハンダは“リール買い”がおすすめ!
電気工作でハンダ付けを始めると、意外とハンダの消耗は早いものです。
最初は少々高く感じるかもしれませんが、500g〜1kgクラスのリールでまとめ買いしておけば、単価が安くなり、結果的にお得です。
ハンダは金属なので、経年による劣化の心配もほとんどなし。
5〜10年かけてじっくり使っても、最後まで問題なく使えます。
ちなみにAmazonで買うなら私のおすすめは、ホーザン(HOZAN)の「H-42-3717」というモデル。
スズ60%/鉛40%の合金で、線径は0.8mmφ。
有鉛だしこのくらいの太さは、電子工作用に向いていますし、個人的にも扱いやすいと感じています。
もちろんフラックス入りなので、そのまま使えて作業も快適。
500g巻で全長約134mと、趣味の製作には十分すぎるくらいのボリュームです。
長く使える安心感があるので、はんだを頻繁に使うようになってきてもすぐに使い切ってしまうことはないので、最初に購入する商品としてはおすすめです。
はんだこての紹介の最後に
今回は、はんだごてやはんだの選び方、さらにおすすめのメーカーを紹介しました。初心者の方は、まず信頼できる製品を選ぶことが、スムーズで安全な作業の第一歩です。
少し高価なものでも、長期的に見れば作業効率が上がり、上達を促進します。自分に合ったはんだごてやはんだを見つけて、楽しい電子工作ライフをスタートさせてください!
それでは、次のプロジェクトがうまくいくことを願っています。これからも、どんどん技術を磨いていきましょう!